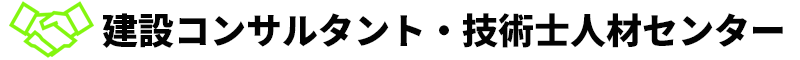就職・転職は「運」 新入社員時代の思い出
就職や転職などは、「大きな人生の選択」だと思います。
大体の人は転職する時に、あそこの会社は、社風が、福利厚生が、将来性が、ブラック情報があるかなど、丹念に調べたりすると思います。
でも結局、最後は「運」が大きく左右します。
なぜなら、会社と言うには、人間が集まって出来ているのです。
どれほど評判の良い会社でも、配属先で上司や同僚に恵まれるとは限りません。
こればっかりは入社してみないと分かりません。
こうした運が左右する人生に対して、どのように対処すればよいのか考察してみたいと思います。
就職は「運」の経験・事例(入社一年目の思い出)
私は、200人位のコンサルに新卒入社し東京技術部に配属されました。同期8名中、東京本社配属は2名(私と、もう一名の同期)だったと記憶しています。
入社した会社は、建設コンサルタントには珍しく、残業も少なく、残業代もやった分は全額貰えるホワイト企業で、本当に良い会社でした。
しかし、私と同期の新卒入社時の上司(教育担当)は、問題がある人でした。
(1)同期の上司はパワハラ・モラハラ
入社後、特定の上司(教育担当)の下について、OJTで技術習得するようなシステムでした。
同期の上司(教育担当)は、パワハラ、モラハラの人でした。
気にくわないことがあれば、怒鳴り散らし、残業や休日出勤は当たり前、残業代も申告させません。
私もそのパワハラ上司の仕事に少し関わった時に、もっと良いやり方があったので、「こっちのやり方の方がよいのでは」と聞いただけで、「生意気なこと言うんじゃね~」から始まって、数分、怒鳴り散らされる経験をしています。
遠くのパーテーションの陰で、諸先輩方が「あいつ、やっぱり怒鳴られてるよ」と大喜びしていました。
この時、東京技術部配属が、私と同期の二名ということは、私の上司がこのパワハラマンになる確率が50%だったことを考えて、内心ヒヤヒヤしたものです。
私だったら、1か月もたなかったでしょう。その場合、全く別の人生を送っていたと思います。
同期は、できた人物で、パワハラ上司と上手くやっており、周りから「猛獣使い」と呼ばれていました。
数年後に、パワハラ上司についた新人などは、やつれてしまって、それは哀れでした。
ある時、呑み会の席で、統括長に、「なぜパワハラを注意しないのか」と聞いたことがあります。その回答は「だって怖くて言えないもん」でした。
「あなたが注意しないで誰が注意するのか」と聞いたのですが、ヘラヘラ笑っているだけで「こりゃだめだ」と思いました。
結局、その新人は中途退職しました。辞める時「なんで私がこんな目に遭ったのでしょうか?」と嘆いていました。
(2)私の上司は、完全放置系(入社1年目)
一方、私は道路部に配属で、最初の上司(教育担当)ですが、わけ分からないおじさんで、朝、「おはようございます」の挨拶した後、無視し何も指示なしです。
仕事が無いか聞いても、面倒くさそうに「待って」と答え、何時間経っても放置です。
正直、理解不能でした。未だに意味がわかりません。
しょうがないので自分で「何か仕事ありませんか?」と他の上司・先輩に営業して仕事を貰っていました。
一年目はテンプレートで図面に数値書き入れ、赤書きした図面直し、平面図を青焼き、切貼り、色塗り、蛇腹折(古いでしょ?)、打ち合わせ資料のコピー作成みたいな、アルバイト仕事ばかりやっていました。
秋頃でしたが、私を完全無視する教育担当がパソコン画面に「人事評価」を表示させたまま、どこかに行ってしまう「人事評価 丸見え事件」が起こったことがあります。
その時の、教育担当の私への評価は、「責任感」、「能力」などすべてが最低点で、唯一「自己啓発性」だけ評価が高くなっていました。
先輩たちから「おまえ、これはやばいよ!」と冷やかされていました。
ほとんど関わったこともなく「他人の下働きしかしてないのに、なんの根拠だよ」と、この時は、さすがにブチ切れそうでした。
どう対処したのか
(1)入社1年目の私の対応
入社1年目、上司(教育担当)から完全無視され、人事評価は最低レベル、他の上司の下働きをして過ごしていたわけです。
しかし、せっかく入った会社、一年間は我慢しようと思い、その悔しさをバネに、必死で自主勉強をしました。
具体的には、専門である道路の技術基準書全般、技術士(道路)の参考書、業務の仕組み等を知るために、RCCMの参考書、共通仕様書、契約約款、あらゆる実務のための書籍、資料を読み漁りました。
※当然、プライベートの時間にですよ。
他の上司の依頼で、入社一年目の年末に急遽受注した山岳部の延長600mの工事用道路設計業務を、実測地形図からペーロケで、路線選定から始まって計画、設計、図面・数量、報告書まで業務一式全部を一人でやることになりました。
これがすごい勉強になりました。
そんな感じで、入社一年目の終わりには道路設計は薄く広く、理解できるようになっていました。
さて、一年間は我慢し、二年目の4月には退社を覚悟で、所属長に教育担当の文句を言うつもりでした。
しかし、社内で、教育担当の私への扱いがひどいという話にはなっていたようで、こちらから文句を言う前に、二年目は教育担当が変更になりました。
(3)会社のエースが教育担当に(2年目)
二年目からの教育担当は、会社のエース、やり手の30代で、口八丁手八丁、声も大きく、若手から恐れられていました。
先輩達から「お前みたいな生意気な奴は、すぐに怒鳴られるだろう」と言われていました。(今度は、パワハラかもと、内心ビクビクしていました。)
今度の教育担当は何事も理詰めな人で、まず業務を任せて、自分で考えてやらせてみて、その内容について確認するという形でした。
業務の最初から、特記仕様書、業務計画書や実行予算も含めてすべて見せていただいて、現地調査も打ち合わせも全部同行です。検討も客先説明も私にさせ、横から補足するような形でした。当然、打ち合わせ簿も報告書も私が作りますし、実務全般を任せてもらえました。
そうやって、すべての情報を共有し、業務完成することを共通目標として仕事する人でした。
業務の中で分からないことを「分かりません」と聞きに行くと怒ります。まず、自分で調べて自分なりの結論を持ってこないと受け付けません。
そうしたやり方は、対応できない人は、怒られてばかりかもしれませんが、私にはピッタリでした。お互いに、良い業務成果をスムーズに完成させるにはどうすればよいかという共通目標で動いていたので、そのための方法論について議論して、決まればそれで一直線と言った感じでした。
しかし、傍から見ると口論にしか見えないようで、他の先輩方から「おまえそんな口の利き方やばいよ」と注意されたりしていました。
当人同士は、お互いすっきりしたもので、何のわだかまりも無かったです。他にもそんな感じの、上司や同僚が複数できました。感覚的には、年齢はばらばらですが戦友に近い感じです。
出張時、業務打ち合わせの終了後は、午後3時だろうが、関係なく、みんなで飲んで直帰です。※今でも飲み仲間です。
そんな感じで、二年目以降は、人間関係にも恵まれ、国交省の大型物件を中心に実績を積みながら、よいキャリアをつけることができました。
就職の「運」の要素への対応方法
前項で述べた通り、就職、転職には、配属や上司、同僚の「運・不運」の要素の影響があります。
転職するにあたって、「運」の要素に対してどう対応すればよいのか、気を付けるべきことを挙げます。
①短期的に成否の判断をしない
不遇な人生を送る人を見ていると、不満を感じやすく「すぐ自棄になる」人が多いように思えます。
「不満」→「怒り」→「制御不能」という感じで、コントロールができない人が多いように思います。
不満に対して感情をあらわにしたり、突発的な行動をとったりすることは、却って、自分の立場を悪くし状況が悪化する負のスパイラルに陥りがちです。
また、特定の誰かに原因を求めて、恨んだり、同じような仲間とつるんで愚痴を言って過ごすことも不毛な行動と言えるでしょう。
次に「会社を辞める」という手段の行使ですが、職務経歴的に一番よくないことは、短期間で転職を繰り返すことです。数か月、長くて1年といった形で、転職を繰り返すほど、転職できる会社のレベルや条件が落ちていく負の連鎖になります。
職場環境に慣れ、転職の成否を判断するには最低1年、できれば3年は必要だと思います。
状況に、一喜一憂せずに、どっしり構えて居るべきです。
※ただし、不満の原因がパワハラや、深夜残業である場合、精神・肉体的限界に達する前に、即逃げてください。心身を壊したら元も子もありません。
②自分がコントロールできることに集中
不満の原因が、自分以外の外部(同僚や上司、組織運営など)であった場合、その多くは、自分ではコントロールできません。
自分でコントロールできない不満に憤慨しても、ストレスで消耗するだけで、決して解決しません。さらに、気づかない内に周りへの態度に現れて、より状況が悪化していきます。
そうしたエネルギーの無駄使いはやめて、建設的なことにエネルギーを集中すべきです。
私の事例では、新入社員時、教育担当に無視されていた期間は、他の上司から頼まれた仕事に誠意を尽くし、プライベートでは、実務の専門技術を自主勉強していました。
恨んだり、ふてくされたりせず、目の前のやるべきこと、自分の価値を高めることに集中したわけです。
だから、その後に、よい機会も巡ってくるし、それに応えることもできたと思っています。
③独立性を上げる(選択肢を増やす)
人間関係(上司、同僚)に恵まれるかという「運」の要素に、人生を左右されないためには、個としての独立性を上げるのが一番です。
例えば、一人で全部業務を回して、会社に貢献できる人材は、上司や同僚との関係が悪くても、接触自体が少ないためダメージは受けにくいです。
また、気に入らなければ別の会社に移ることは容易です。
※「いつ辞でもやめられる」、選択肢が多いと、不思議につらくなくなります。
ところが、一人で業務を回せない人は、業務において、誰かの指示や助けが必要です。そこで、様々な軋轢や嫌がらせを受けて、苦悩が起こります。
さらに、一人で業務を回せない人は、人材の価値は低いですし、別の会社に移っても同じ状況となるかもしれません。
参考記事:建設コンサルタントは20代が一番きつい
また、○○がないと業務ができない、~業務しかできないなど、制約条件が増えるほど組織に依存しなければなりません。専門が細分化された大手出身者に割と多い傾向があります。
④環境を変える決断力(引き際を知ること)
投資で一番難しいのは「損切り」ですが、同じく人生の中で、戦略的に「撤退」の判断することは難しい決断の一つです。
人間、つい意地になって限界を超えて我慢してしまいます。前記の①~③、自棄にならず、恨まず、戦わず、やるべきことに集中し、自分の価値、独立性を高める行動をしてきたら、もう十分、最善を尽くしています。
それでだめなら、あとは「戦略的撤退」、自分の意思で会社を辞めて環境を変える(転職する)だけです。
おわりに
不毛なものに関わらず、どっしり構えて、自分でコントロールできる「やるべきこと」に集中し独立性を磨き、最善を尽くしてもダメなら「戦略的撤退」するという生き方をしてください。
そうすれば、どれほど「運」が悪くても、必ず「運」をコントロールして、周りから尊敬感謝されて、裁量・自由度高く働いて、価値に見合った報酬もいただける。そういう人生が送れます。
現状、不遇を感じている人も、そうやって充実した人生を歩まれてください。
ご参考になれば幸いです。
![]() このコラムをシェアしていただけると嬉しいです。
このコラムをシェアしていただけると嬉しいです。