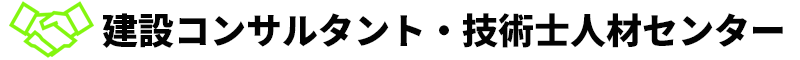建設業界「勘違い進路」あるある集
建設分野に進む理由として、「デザイン」、「環境」、「都市計画」、「橋梁計画」といった華やかなイメージに惹かれたことを挙げる人が多いようです。
でも、将来の進路を、イメージだけで決めてしまうと、進学や就職してから、「思っていたのと違う」となってしまいます。
これから、建設分野への進学や就職を考えている人に、参考にしてもらうために、ありがちな勘違い事例を紹介してみたいと思います。
- 1. 勘違い進路の事例
- 1.1. ①橋梁設計がしたくて、大学の建築科に進学する
- 1.2. ②都市計画がしたくて、大学の建築学科に進学する
- 1.3. ③橋梁設計がしたくて橋梁メーカーやゼネコンに就職する
- 1.4. ④都市計画がしたくてハウスメーカーやゼネコンに入る
- 1.5. ⑤有名大学院卒で、県土木に入ったら、仕事がパトロールだった。
- 1.6. ⑥建設コンサルタントは「先生業」ではなかった
- 1.7. ⑦希望ではない部署への配属
- 1.8. ⑧希望部署に配属されてもイメージと違い失望
- 1.9. ⑨上司・同僚
- 2. 勘違いが発覚した後の対応方法
- 2.1. ①「すぐ辞める」or 「このまま我慢して働く」という二択について
- 2.2. ②「我慢して働く」場合の対応
- 3. 夢を叶えるための対応方法
- 4. おわりに
勘違い進路の事例
①橋梁設計がしたくて、大学の建築科に進学する
テレビドラマで、建築士らしき人が、パワポで橋梁形式のプレゼンしている華やかなシーンを見て、建築科に進学する人もいると思います。
欧米では、建築家も橋梁設計するらしいのですが、日本の場合、橋梁設計をするのは建築士ではなく、土木分野で、必要な資格は技術士(建設部門 鋼構造コンクリート)です。
建築士になっても橋梁設計はできませんので注意しましょう。
②都市計画がしたくて、大学の建築学科に進学する
大学の建築学科では「田園都市論」など、都市計画についてはかなり学ぶと思います。
でも、日本では、行政の発注する都市計画業務(マスタープラン作成等)を、受注しているのは主に建設コンサルタント会社で、必要な資格は技術士(建設部門 都市計画)です。
技術士一次試験(建設部門)は、土木分野の幅広い知識が要求されますので、注意しましょう。
③橋梁設計がしたくて橋梁メーカーやゼネコンに就職する
橋梁は、ほとんどが公共事業になりますが、公共インフラは設計施工分離といって、計画設計は、行政(実際は、代理人として委託を受けたコンサルタント)、ゼネコンやメーカーは制作・施工をしています。
橋梁メーカーというのは、基本的には上部工(橋げた)の制作と架設をする会社で、鋼橋やPC橋などメーカーが分かれています。
メーカーが行う設計は、制作設計と呼ばれるもので、コンサルの詳細設計に対して、さらに溶接(鋼橋)や、温度収縮、自重によるたわみ等まで考慮して、工場や現場で制作するために0.1mm単位での超精密な上部工の設計を行います。
ゼネコンは、下部工(橋台、橋脚)等の仮設の設計や、基礎構造等の設計変更等がおこる場合、自社内の設計部等で修正設計をする場合があります。
橋梁では、上部工詳細設計付き施工発注(デザインビルド)もありますが、その場合、形式、寸法等すべてき決まった状態でメーカーが上部工の制作設計をします。
海外事業の本格的なデザインビルド案件の場合は、ゼネコンの下にコンサルが入って設計している場合がほとんどです。
皆さんがイメージする華やかな橋梁計画、橋梁の形式を比較したりデザインする仕事は、「橋梁概略設計」「橋梁予備設計」と呼ばれるもので、建設コンサルタントがやっています。
ゼネコンで、橋梁形式の計画等の仕事をやれる可能性は、民受のリゾート施設やゴルフ場内の小橋梁を設計するくらいです。
ゼネコンやメーカーのホームページには、橋梁設計をしているような画像が入っていますが、この辺は企業のイメージ戦略ですので、橋梁形式選定レベルの橋梁計画・設計がやりたい人は勘違いしないようにしましょう。
④都市計画がしたくてハウスメーカーやゼネコンに入る
「都市計画」や「街づくり」といった言葉は、響きが恰好よいので、様々な業種の企業が自社の事業として挙げています。
住宅メーカーは、宅地開発をする場合は、街路や公園を作りますし、商店街の再生やショッピングモールの開発プロジェクトでも、諸施設の配置やデザイン等も当然必要になるので、嘘をついているわけではありません。
ただ、希望する「都市計画」の内容が、市町村レベル以上の広域なものであるなら、公務員になって都市計画系の部署に配属されるか、建設コンサルタントの都市計画部に入社する必要があります。
⑤有名大学院卒で、県土木に入ったら、仕事がパトロールだった。
当社に寄せられた事例では、旧帝大の院卒で河川専攻の方が、県土木に入ったら、道路維持管理の出先機関に配属で、毎日パトロールの仕事だった。
しかも、ルールで30代までは出先で修行という話がありました。
国家一種のキャリア官僚ならエリートコースがありますが、都道府県や市町村等にいったん入庁したら、いくら学歴がすごくても、特別なエリートコースはありません。
本当に自分の専門性を追及したい人は、気を付けましょう。
⑥建設コンサルタントは「先生業」ではなかった
建設コンルタントは「先生業」的な感じで、礼儀正しい顧客(行政職員)に、専門家として尊敬されながら仕事をするものだと思っている人が多いと思います。
しかし、実際は、横柄な発注者(役人)にペコペコ頭を下げながらをしている建設コンサルタントの姿を見ることも多いです。
日本の建設コンサルタントの契約は、総価、一式で契約する非常に片務的なもので、発注者(役所)が粗さがしすれば、コンサルをいくらでもイジメることができます。
だから、コンサル側は、発注者から、理不尽な要求をされても基本的には逆らえません。
ありがちなのは、金曜の夕方に電話してきて、月曜朝一での検討資料提出を命じたり、些細なことで揚げ足をとって、怒鳴り散らしたり、何度もやり直しを命じたり、明らかにそういうことを楽しんでいるような、病的な人が存在します。
立場が人を狂わせるのは、良くあることです。
悪意剝き出しの人に遭遇するのは、結構、ショックな出来事です。
ただ、大部分はまともな人なので、そんなに心配しなくても大丈夫です。
役所側の担当者も、受注者を選べないので、「〇〇コンサルにやってほしかったのに、なんでお宅が受注したんだ!」と言われたこともありすし、「ポンコツ人材」がコンサル側の担当者で発注者が困り果てている姿も見ることもあり、同情することもあります。
最初は横柄だった発注者が、徐々にフレンドリーになってきて、業務外の技術相談が来たりすることが、仕事のやりがいを感じる時です。
⑦希望ではない部署への配属
建設コンサルタントに入社する人は、かなりの率で橋梁、環境、景観デザイン、都市計画、交通計画のどれかを志望します。
しかし、実際の配属では、道路や河川、土基礎、トンネル、下水道など希望ではない部署の配属になる可能性は高いです。
また、配属先の技術分野の専門家として一生を過ごす可能性が高いため、人生の大きな分岐路になります。
これまで、希望しない部署に配属され、不貞腐れてしまっている人を、何人も見て来ました。
⑧希望部署に配属されてもイメージと違い失望
せっかく希望部署に配属されても、失望してしまうケースもあります。
まず、環境や都市計画といった部署は、建設コンサルタント社内では、多くの場合、花形部署ではありません。
理由は、手間の割に金額が安い仕事が多くて、儲からないからです。どちらかといえば、万年赤字で、お荷物部署とされる場合が多いです。
※これらの部署が存在する意味は、「総合コンサルタントのプライド」や上流工程を抑える等の意味はあります。
また、業務内容自体の失望もあります。
例えば、都市計画といっても、ゼロから都市をデザインするわけはなく、委員会や議会や住民説明といった中で、既得利権のぶつかり合い、天の声や、理不尽なことに遭遇しながら利害調整するような役割をコンサルタントがすることも多いです。
橋梁部門も、現在は、新規より点検補修といった業務が増えていますし、橋梁設計といっても、上部工と下部工で専門が別れ、上部工も鋼橋とPC・コンクリート橋でさらに専門が分かれています。
橋梁予備設計等の形式比較等も、交差道路の建築限界や河川条件、地質等の制約条件を踏まえた中で、径間長、基礎形式、上部工形式等の最適な組み合わせ(経済性、施工性、維持管理性等)を見つける作業であって、美術的なデザインと違って、ほとんどが地道な作業です。景観・修景設計等は、ランドマーク的な橋梁において稀に行われるくらいです。
このように、花形部署に配属されたと思ったら、実は勘違いだったという人もいます。
⑨上司・同僚
建設コンサルタントの社員は、名前の響きからして技術の専門家集団なのだから、皆、勉強家で優秀な人が揃っていると思っている人も多いでしょう。
私も新卒入社直後は、諸先輩方は、専門知識が豊富で優秀に見えました。
でも二年くらいたつとだんだん見えてきます。
一番ショックを受けたのが、あまりに勉強しないことです。
自分の専門分野の技術基準等も読み込まず、OJTで業務上必要なところだけ見る感じの人がほとんどです。
契約や仕様等の法的な部分もベテランでも理解しないで働いている人が多数です。
有名大学院卒の人も、技術士等の資格の勉強はしますが、業務能力を上げるための活動はあまりしません。
独立志望もなく、サラリーマン意識で、一生会社で過ごすつもりの人ばかりです。
また、いい年した中高年で、信じられないほど幼稚な、嫌がらせや、パワハラをするような人も見受けられて、人間って、年齢を重ねても基本的には成長しないものだと思いました。
まあ、でも建設コンサル業界は、個人が業務を受け持つので、同僚や上司との人間関係は、それほど濃くありませんので、人間関係は楽だと思います
人間関係で問題が起こりやすいのは、若手の下積み期間や、中途入社後の数年、あるいは社内の権力闘争に巻き揉まれた場合だと思います。
勘違いが発覚した後の対応方法
入社後に、自分の希望が叶わなかった場合や、イメージと違って失望した場合、どのような対応をすべきなのか、悩ましい問題です。
①「すぐ辞める」or 「このまま我慢して働く」という二択について
この中で、「すぐ辞める」という行為は、かなりリスクが伴います。
一つ目のリスクは、短期で辞めた人材は、その後の転職市場での価値が、だいぶ下がる点です。企業側は、「採用しても、すぐ辞めるのでは」と考えるからです。
二つ目のリスクは、「嫌だ」→「辞める」という行為をした瞬間は、解放感に包まれます。そして「辞め癖」がついてしまう恐れがあります。
ただ、パラハラや、詐欺ギリギリの職務を強要されるような即逃避すべきケースもあるので、辞めるときは、こうしたリスク面は考慮しながら自己判断してください。
②「我慢して働く」場合の対応
入社後に、職場や仕事に大きく失望したものの、「我慢して働く」ことを選択した場合ですが、以下の三つの選択肢があります。
a.「俺はこんなことやりたくなかった」と不貞腐れて、適当な仕事をする
同類とつるんで、同僚や後輩を仲間に引き入れる。
b.失望はしても、せっかくの縁なので、その状況を受け入れ前向きに仕事をする
c.仕事をしながらも、将来、転職して自分の希望を叶えるための勉強や資格取得を続ける
建設コンサル業界における実態としては、3割くらいが「a.不貞腐れて適当に仕事する」になります。残りの7割の人は、「b.境遇を受けいれる」を選択し、頑張ります。
「c.将来の夢の実現のために、勉強する」の人は、あまりいません。
10年後の「a.不貞腐れて適当に仕事する」の人は、会社に居づらくなって辞めているか、夢も希望もなく、惰性だけて生きている中年になっています。
夢を叶えるための対応方法
入社後に希望と違っても、諦めず将来の夢を叶える確率が最も高い方法について、考えてみます。
ありがちですが、「自分の希望をしつこく要求し続ける」とか、「希望の会社への転職に何度もチャレンジする」方法は、どうでしょうか?
ある有名企業には、毎週、同じ人が応募してくるそうです。
また、転職希望者で、大手ゼネコンで施工管理をしていて、次の希望転職先は、「戦略コンサルタント」という感じの人がいます。
施工管理経験だけで、経営の知識が皆無なのに、戦略コンサルタントへの転職希望する発想が理解できません。
その他に、都市計画希望と言いながら、都市計画の知識がゼロ、経理希望と言いながら簿記も持っていない、海外勤務希望なのに英語力ゼロ、そんな人がゴロゴロいます。
入社したら会社が教育してくれると考えているようです。
もし、あなたが採用担当者で、未経験者を採用する場合、「専門知識や関連資格がある人材」と「専門知識も資格もない人材」が来たら、どちらを採用しますか?
それ相応の行動もせず、しつこく自分の希望を要求し続ける人は、現実には、多く見受けられます。恐らく過去の「ごね得」した成功体験がそうさせるのでしょう。
しかし、こういう人は、不毛な要求闘争を続けるか、美味しい話に騙されるか、禄でもない結末になる可能性が高いです。
将来的に、自分の夢を叶えたければ、入社した会社や部署が希望と違っていても、それなりに経験や実績が積める職場であるなら、まずはそこで3年くらいは、踏ん張って、その分野をある程度、極めてしまうことを勧めます。
それにプラスして、希望分野の自主勉強や資格を取得して、「社会人の実績」プラス「希望分野の知識」を売りにして、希望を要求したり、転職活動をすることが、夢の実現には一番の近道だと思います。
おわりに
一般的に、外から見て、華やかな仕事や、難しい仕事ほど、実際にその仕事に就けた場合、「思っていたのと違う」となる確率が高いはずです。
例えば、プロスポーツ選手は、普段の生活は地味で過酷なトレーニングが大半なはずです。医者や弁護士や研究者も、実際は、地味で辛い作業が大部分です。
建設コンサルタントも同様、地味で辛い作業が多いですが、それ以上に何かを計画設計する。ゼロから創造する仕事というのは、想像もしなかった面白いことが多いです。
また、私が起業・独立した時は、独立前にイメージした世界とは、8割くらいは「思っていたのと違う」世界でしたが、それによって、却って楽しめたと思っています。
就職において、どこかにある理想のホワイト企業を探し求める生き方もありかもしれません。
しかし、挑戦的な仕事をしたい人は、「思っていたのと違う」を前提として、まずは「仮説」を立てて、実際にその世界に飛び込んでみて、良い意味でも悪い意味でも「予想を裏切られた」を実体験し、検証し、またチャレンジを繰り返す。
という感じの生き方の方が、最終的には成功率も高いですし、何より楽しめると思います。
皆さんのご参考になれば幸いです。
こちらの記事もどうぞ↓